顔の骨折や外傷も
耳鼻科で診ています
外傷を耳鼻科で治療することがあるのかと思われるかもしれませんが、耳鼻咽喉科頭頸部外科の名の通り、耳鼻科医師は基本的に外科医の系統ですので、外傷の治療はもちろん対応しております。
具体的に身近なことで一番多いのは鼻骨骨折ですが、それ以外のケースについても、私自身の経験を踏まえ、記載していこうと思います。
鼻骨骨折
一番多いのが鼻骨骨折です。よく整形外科に先に行かれ、整形外科の先生から、「これは耳鼻科に行ってください」といわれ、いらっしゃるケースが多いですね。
バスケットやバレーボールなどの球技をしているときに相手選手の肘が顔面に当たるケースが多いですが、野球のボールが顔面に当たるケースなどもあります。
鼻骨は鼻根部という鼻の付け根に位置する顔面骨の1つです。
骨折が起きると、内側にめり込むような形となることが多く、美容的に気になるケースや、あるいはメガネをかけている方だと、うまくメガネをかけられなくなることがあります。
整復できる期間に限りがあるため、早めに受診しましょう
受傷後2週間程度で骨折した状態の骨が癒着するため、骨折を整復できる期間は2週間以内となり、できれば受傷後1週間程度で方針を決定する必要があります。
受傷された場合は、早めの受診が望ましいです。
稀に、野球の試合でファールボールが当たり、目のあたりまで当たってしまったというケースで眼球破裂となっていたといった件を聞いたことがあります。
きわめて稀なケースとは思いますが、お子さんでのケースと伺いました。
外傷が起きた場合は、自己判断で済まさず、診察を受けたほうが安心です。
顔面骨骨折
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、顔の骨折のことを指します。
鼻骨骨折も広義では顔面骨骨折の中に含まれますが、我々耳鼻科医の中で顔面骨骨折というと、
- 御老人の方が転倒し顔面を床に打ち付け顔面骨に何本かひびが入るケース
- DVや喧嘩などで顔面に強く高エネルギーの力が加わり骨折するケース
- 交通外傷、特にバイク搭乗者が事故で顔面をぶつけ、ひどく骨折を起こしているケース
などがあります。
さまざまな専門科の先生と連携し治療します
救急科の先生の対応
交通外傷の場合は、顔面だけでなく体幹や四肢にも外傷が及んでいることがほとんどであり、救急搬送されICUなどで管理されることがほとんどです。
体幹の問題が落ち着いた後、耳鼻科に連絡が入り、顔面骨骨折の評価を行います。
私も大学病院で当直をしていたときはたまに連絡を受けていましたので、ICUに行くことも多く、自然と救急科の先生と顔見知りになっていくことが多かったです。
かみ合わせを調整する歯科の先生
顔面骨骨折については、骨折の分類法があり、それと咬合の状況を見ながら、整復方法について方針を決定します。
大事なことはかみ合わせであり、歯科の先生も入ってもらい、骨折の整復は顎間固定による歯の固定と、頬骨や前頭骨などの折れていない骨からのプレート固定によって、橋をつなぐように骨をつないでいきます。
私が骨折治療をしていた頃は、吸収性プレートを用いた整復が主体となっていた時期でしたが、以前まではチタンプレートなどを用いていたのではないかと思います。
吸収性プレートは抜去する必要がないため便利ですが、硬性が金属と比較し弱いため、その点を理解しておく必要があります。
眼科の先生による視力や視界の評価
また、顔面骨骨折の場合、眼窩下骨折といって、眼球の周りを覆っている骨が骨折し、眼窩内脂肪織と言われる眼球の周りの脂肪が、主に上顎洞の中に入り込んだり、あるいは眼球運動に関係する筋肉がはまり込んだりして、うまく眼球が動かなくなることがあります。
症状としてはモノが2重に見えるという複視などが挙げられます。
この場合、鼻内からも手術し、嵌頓した組織を外して持ち上げた上で、副鼻腔内にバルーンなどを入れ骨折した眼窩底部が再度嵌頓を起こさないようにしばらく固定するなどといったことを行うことがあります。
もちろん眼球が破裂したり、眼球内部に問題が起きていれば、視力が落ちていたり、見てくれにも問題が起きていることが明白であることもあります。
眼科の先生にも診察いただき、眼球についての評価をお願いすることとなります。
脳神経外科領域での検査
また、頭蓋底といって、脳と鼻の境をなしている骨に骨折があった場合、髄液漏といって脳を守っている髄液という体液が、鼻腔内に漏れてしまうこともあります。
CTなどで頭蓋底骨折を積極的に疑う場合、骨折部位に対するアプローチもしっかり検討する必要があります。
また、骨折のパターンによっては、側頭骨骨折といって、内耳に影響がある部位が骨折していることがあり、それらの評価も必要です。
このように、顔面骨骨折は、主に耳鼻咽喉科頭頸部外科・歯科・脳外科・眼科による総合的な評価及び介入が必要であり、主に耳鼻咽喉科頭頸部外科が主体となって介入する外傷です。
蛇足ですが、長期気管挿管の患者さんの場合、気管切開へ切り替えなければならない時期が来ますが、基本的に待機的気管切開術は耳鼻咽喉科が担当します。
従って、耳鼻咽喉科医がICUに出入りする機会は多く、特に大学病院勤務時代は、私もよくICUに出入りしていました。
顔面外傷
顔面骨骨折と被るのですが、骨折ではなく、表層の筋肉や耳下腺、外鼻の外傷なども治療します。
これらの外傷が程度の強い状況で起きることは珍しく、私が経験したケースでも、水上バイクでの接触事故、工場で機械が破損し顔面と接触したケースなど、かなり稀なケースで発生します。
鼻については、外鼻は、基本的に硬性組織は軟骨が主体であるため、デブリードマン及び回復後の審美的な形状を意識しながら縫合するようになります。
顔面の縫合については、耳下腺の断裂があった場合、すでに顔面神経が断裂している可能性が高いのですが、耳下腺を被覆した状態で縫合しないと、フライ症候群(Frey症候群)を誘発するため、被覆する層を間違えないようにしながら手術を進めていきます。
頸部の外傷
頸部が単独で外傷を起こすことはかなり稀ですが、喉仏のあたりを強くぶつけてしまった場合、甲状軟骨が壊れてしまっていることもあり、気道狭窄の危険性があります。
気道が詰まると死に直結しますので、直ちに評価が必要です。
それらが落ち着いてから、きたしているであろう発声障害についてアプローチするようになりますが、これについては耳鼻咽喉科頭頸部外科の中でも音声外来を担当する専門チームに任せることになると思います。
包丁などで頸部を切ってしまっている場合、そもそも総頚動脈や内頚動脈が切断されていれば出血多量にて、早々に致死的となっている可能性が高く、救命そのものが難しいと思われます。
しかし実際のところ、そこまで深く切れているケースは少なく、表層の筋層や皮下組織、表皮の縫合ですむことも多いです。
しかし頸部は神経が多く張り巡らされているため、ある程度の皮膚感覚の脱失などは避けられないでしょう。
歯ブラシ外傷
実際には箸などでもおきますが、小児で特に気を付ける外傷です。
箸や歯ブラシを口にくわえたまま歩いたりすることで、それらでのどをついてしまい、場合によっては内頚動脈解離、頭蓋底穿破などを起こすことが稀にあります。
まさかそんなことが起きるはずがないと思うかもしれませんが、特に内頚動脈は喉の少し奥を走行しており、意外と危険な場所なのです。
なかなか歯ブラシを咥えたまま歩かないでといっても、子供たちは聞く耳を持たないこともありますが、危険な行為ですので、じっと歯磨きができるようになるまで、しつこくてもよいので教えてあげることが大事です。
鼓膜穿孔・耳かき外傷
- お子さんの耳掃除の際に鼓膜を破ってしまうケース
- 保護者の方が耳掃除をしているときに子供が近づいてきて力が加わり、
鼓膜穿破してしまうケース - 稀ですが、平手打ちをされたり、あるいは剣道をしていて竹刀が耳に当たり鼓膜が破れるケース
があります。
鼓膜は再生するのでしょう、と思われるかもしれませんが、破損範囲が広い場合、穿孔(穴)が残ることもあります。
また、耳小骨離断となってしまった場合、鼓膜が閉鎖しても聞こえは元に戻りません。
中耳まで外傷が及んだ場合、治らないめまいと難聴となり、緊急で手術を検討しなければいけない状況となります。
俗に耳かき外傷などと呼んだりしますが、最悪なケースも想定した上で診察に臨む必要があります。



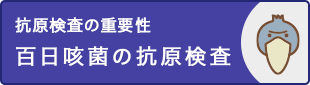
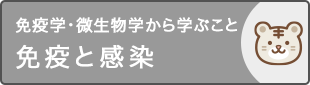
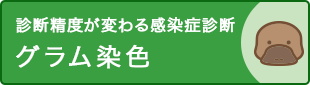










- 耳の病気
- 急性中耳炎
- 慢性滲出性中耳炎
- 良性発作性頭位めまい症
- メニエール病
- 突発性難聴




